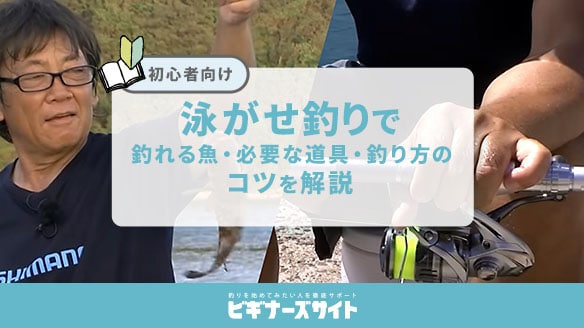2025/09/19
コラム
座布団級も期待できるヒラメジギングの聖地・福島・久ノ浜。山本啓人が攻略!

東北でも有数のヒラメの好漁場として知られる福島県沖。このエリアは、ヒラメをメインターゲットにしたジギングが盛んな地であり、出船地は大きく分けて南から小名浜エリア、久ノ浜エリア、北の相馬沖とポイントは分かれる。今回は久ノ浜沖へ山本啓人さんが釣行。数、型ともに期待できる夏場の乗っ込み期を狙って訪れ攻略した。
数、型ともに期待できる久ノ浜沖のヒラメジギング
今回、山本さんが福島県・久ノ浜に訪れたのは、7月中旬。久ノ浜沖は、例年6月から9月頃にヒラメのジギングが盛んになる。それはこの時期に、このエリアではヒラメの乗っ込み期に重なるため、数、型ともに期待できるからだ。条件が良ければ、1人10枚以上という釣果も珍しくなく、さらに80cmオーバーが上がることも多い。山本さんは、スーパーライトジギングからビッグゲームまで、様々なスタイルで日本全国を訪れるジギングのエキスパートだが、他のジギングでヒラメを釣り上げたことは数多くあるものの、今回の福島釣行のようにヒラメをメインターゲットにしたジギングの経験は無かった。そこで2025年7月に相馬沖、今回の久ノ浜沖を舞台に釣行を計画した。しかし前日の相馬沖は、終始潮が動かず苦戦。水温が例年より低く、さまざまな魚が釣れて五目釣りとしては楽しめたものの、ヒラメの釣果は盛期と言える状態ではなかった。山本さん、同船者ともに、数枚のヒラメを釣り上げたが、中型、小型で、福島らしい特大サイズは出ず、数も乏しい状況であった。この日の久ノ浜からの出船では、相馬沖よりも南の海域を攻めるため、水温が少しでも高いことを期待した。ただ、沖へ船を出すと、天気は良かったが、朝のうちは風が冷たかった。これにより水温が低いことが容易に想像できた。

山本さんにとって初めての福島釣行。以前から、この地がヒラメで盛り上がっていることを知っていたが、なかなかそのチャンスが訪れなかった。今回、友人の誘いによって、初挑戦することに。
ちなみに久ノ浜沖の過去の実績を見ると、年によって好調の月はまちまち。7月が絶好調の年もあれば、8月や9月まで待たないと爆釣しない年もある。ヒラメの“乗っ込みのタイミング”次第で釣果は大きく変わるのだろう。しかし、タイミングさえ当たれば…他のエリアではまず味わえない大物との出会いも夢じゃない! そんな釣りが楽しめるのは、福島県のヒラメを狙っている船は、50cm以下はリリース、さらにキープ数を設けるなど、レギュレーションがあるからだろう。レギュレーションは船が所属している漁協よって異なるが、これらがこの地のヒラメの魚影の濃さに繋がっていると考えられる。
初挑戦の久ノ浜沖でのタックルファーストチョイス

フィールドの状況、ベストな誘いなどが分からない初場所だったために、前日に楽しんだ相馬沖釣行で良かったタックルをセレクト。ここから、この地のベストを探していく。
さて、実釣の状況だが、山本さんが最初に選んだタックルは、前日の相馬沖での経験を踏まえたものだった。ロッドは「オシアジガー フルベンドB60-1」、リールは「オシア コンクエスト300HG」。これにPEライン1.5号(プロト)を巻き、リーダーは「オシアジガー マスターフロロ」8号を結束した。ジグは、セミロングタイプでリア重心のプロトジグ「シックスライド140g」を選択。フックは前後に#2/0サイズのツインフックを装着している。
船はポイントに入り、水深43mで釣り開始のアナウンスが流れた。このエリアのポイントは魚礁や根周りを狙う。魚礁の高さは約3m。ボトムから10mほど上までベイトの反応が映っているという。
山本さんは語る。
「ラインはPE1号や1.2号でもいいですが、大型ヒラメを狙うなら1.5号が安心だと思います。また、この海域の魚礁には小型ながらイシナギもいると聞いているので、そういったことも踏まえて1.5号がベストだと思います」
山本さんはジグのベストな動きを探っていく。スライドさせるのか、フォールを浮遊させるのか、バックスライドさせるのかなどを確認していく。これは彼のジギングでの基本的な流れだが、久ノ浜沖は初めてのフィールドであり、より慎重に見極める必要がある。ファーストチョイスにリア重心ジグを選んだのは、前日の相馬沖ではフォールで大きく飛ばないジグのほうが反応が良かった経験によるものだ。
スロージギングによるファーストヒットと時合
ヒラメは視覚が狭く、その視野の中で動くものに反応する。視覚から外れると反応しなくなるため、その中でジグを動かすことが大切だ。そのため速いシャクリ上げでなく、棚を細かく刻む誘い、フォールの動きを活かした誘いが有効になる。スロー系ジギングは、ヒラメの食性に合った探り方といえる。
この日、山本さんは朝の早い段階で、ボトムから7シャクリ目で喰わせた。魚礁のポイントは、魚礁の上に魚がいることもあり、着底から離れている位置でもヒットに繋がることがあるため、気を抜かずに上層までしゃくり続けることが大切だ。
ロッドをしっかりと曲げたこの魚は、アイナメだった。周りには鳥が舞い、時折、水面へ突っ込み雰囲気は良い。水面には何かに追われているベイトフィッシュも見える。中層では遊泳力のある魚がベイトフィッシュを追い、ボトム付近の魚たちは中層回遊魚に襲われてダメージを受けたベイトフィッシュ、追われたベイトフィッシュを捕食しているのかもしれない。メインターゲットであるヒラメは、ボトムでベイトが近くを通るのを待ち伏せしている魚だが、上から落ちてくるベイトフィッシュにももちろん反応する。またベイトフィッシュを追って移動し、ベイトを追いかけて棚を上げることもある。ベイトフィッシュの反応があるのは良い状況なのは間違いない。
朝から魚たちの活性は高いようだ。すると後方のお客さんに大型がヒット。PE1.5号の細糸のため、慎重にやり取りして上がってきたのは8kgほどのブリ。続いて別のアングラーがランディングしたのは、5kgのマダイだった。

ファーストヒットは、魚礁の上付近でヒットしてきたアイナメ。
開発中にプロトジグはヒラメに最適!

周りの釣果の様子を見つつ、活性が高いと判断して中層まで誘うとヒット。すぐに青物だと判断できる走りを見せた。ライトタックルのため、慌てずにやり取りを行う。

ランディングされたのは予想通り青物。ジグを飲み込むほどの高活性。
時合と言える状況の中、山本さんもすぐにヒットさせた。これはすぐに青物と分かる引きを見せた。予想通り上がってきたのはイナダだった。上までしゃくり上げると、活性の高い青物がヒットしてしまう状況だが、ヒラメも高活性であればジグを長く追い、喰ってくることもある。青物を避けるなら、どこまで誘い上げれば良いのか判断が難しい。
山本さんはチャンスタイムであったため、撮影を終えて素早くジグを投入すると、すぐにバイトを得た。ボトムから離れた位置でヒットしたこの魚は、強い引きであったためにまた青物かと思われたが、なんと本命のヒラメ。肉厚のコンディションの良いヒラメだった。ジグは変更なくプロトモデルのシックスライドだ。
このジグはジャーク後に水平になり、素早くバックスライドする独自のアクションが特徴。これまで2年ほどテストを行い、サクラマス、多彩なターゲットにおいて高い実績を収めてきた。
「多くの実績を持つシックスサイドを、優雅にバックスライドするようにしたのがシックスライドです。サクラマスでは特に高い釣果を記録し、根魚狙いではスピードのあるフォールで反応を引き出せます。また、飛距離を抑えたフォールは視界の狭いヒラメに有効だと思います。また薄いボディによりジャークでの抜けの良さも備えており、スピニングタックルを使った青物狙いでも活躍します。幅広く活躍するジグです」



また青物かと思ったが、本命のヒラメだった。肉厚のグッドコンディション。

続けてメバルもヒット。尺サイズのナイスな個体。
魚礁攻略のポイント

魚礁を攻める場合は、その存在を意識しながらさぐることが大切。
今回の久ノ浜沖では、魚礁がメインの狙い場となった。魚礁を攻める際の注意点について、少し上まで探ること以外の注意点を山本さんが解説してくれた。
「魚礁が入っているポイントでは、長い距離のフォールを入れず、短めにシャクリ上げていきます。長い距離のフォールで魚を追わせ喰わすと、そのまま魚礁の隙間に潜り込まれてしまう可能性があるからです。とくに根に潜る習性のある魚を狙う場合は、フォールを短くすることで根に潜られるリスクを回避できます」
ヒラメが魚礁に潜り込むことはほとんどないが、イシナギや大型ソイなど、ヒット後の突っ込みが強い根魚のヒットの可能性がある時は要注意だ。
さらに、魚礁で底物を探る際は「ラインを斜めにしないこと」も重要だという。船が流されてラインが斜めになると、ジグが引いてくる途中で魚礁に接触し、根掛かりのリスクが増える。斜めになったら一度回収し、真下に入れ直すのがベストだ。
「もう一つ大事なのは、アタリがあった時にすぐアワせないことです。ワンテンポ我慢して見極める。底からシャクリ上げるとき、ジグが魚礁に当たることがあります。これをアタリと勘違いして即アワセを入れてしまうと、根掛かりしてしまいます。コツンときた時に“魚か岩か”を見極める、その一瞬の我慢が大切です」
そんな解説をしていると、フォールでアタリを捉えた。最初は掛からなかったが、クラッチを切って少し落とし、再びジャークを入れると今度はしっかりフッキング。ボトム付近で強烈に粘る魚を、オシアジガー フルベンドB60-1をしっかり曲げて浮かせにかかる。強い突っ込みを耐えきって上がってきたのは、大型のクロソイだった。

ボトム付近でバイトした魚は、強烈な引きを見せた。ロッドを曲げて魚礁への魚の突っ込みを制御。


上がってきたのは、大型のクロソイ。このサイズが釣れるのは、海が豊かな証拠。
ロッドセレクトの考え方
今回、山本さんは「オシアジガー フルベンド」の1、2パワー、「オシアジガー インフニティ モーティブ」の1、2、3パワーを持ち込んでいた。このロッドセレクトについて山本さんはこう語った。
「使用するジグウエイト、大型のヒラメ狙いということで、それぞれのモデルのロッドパワーを選んできました。ただ今回の反省点は、フルベンド、モーティブの0パワーを持ってこなかったことです」
0パワーを選ぶ理由は、ジグをよりゆったりと動かしたい場面があったからだ。実際、1パワーでも「少しジグの跳ね上げが強い」と感じたという。パワーのわずかな差がアクションに大きく影響する。

ジグをどう動かすかによって、ロッドのパワーは選ぶ必要がある。今回の釣行時は0番がベストだったと判断。
モーティブか、フルベンドか?
では、モーティブとフルベンド、どちらのセレクトが良いかと言う問いには、今回はモーティブのほうが合っていると感じたとのこと。理由は、誘い上げよりフォール主体の攻めが有効だったこと。モーティブの6フィート10インチの長さがあったほうが、よりフォールでの誘いを演出しやすいからだ。加えて今回の久ノ浜沖では船が大型だったため、水面からの高さを考えると長いロッドのほうが扱いやすい、という判断もあった。ちなみにモーティブとフルベンドを同じ番手で比べると、モーティブのほうが長さがあることでハリがあるとのこと。そのため、よりハリが少なく0パワーに近いフルベンドB60- 1をまずは選択した。
「今回の状況ではフルベンド、インフィニティ、リミティッドなら1パワーで良いですが、モーティブなら0パワーがベストだと思います」
ちなみに「オシアジガー インフィニティ モーティブ」は、6フィート10インチの長さを持ちながら、軽快にジャークできる設計が特徴だ。スローテーパー化されたブランクスは、曲がりの支点が手元寄りにあるため操作性が高く、潮の変化やジグの挙動も捉えやすい。さらに、長さがあっても反発力がしっかりしているため、軽い力でジグを跳ね上げられる。グリップジョイント仕様により、仕舞寸法は162.1〜163.5cmとコンパクトなため、山本さんのように航空機を利用する遠征スタイルでも携行しやすいのも大きな魅力だ。

モーティブとフルベンドを同じパワーで比べると、モーティブのほうが若干ハリが強い性能という。それは長さがあるからだ。
タックルを大きくチェンジして攻略
潮止まりを迎えると、それまで出ていたアタリがピタリと止まった。このタイミングで山本さんはジグチェンジを決断。ウエイトも替えながらアタリパターンを探し直していく。ヒットが遠い時間帯ではあるが、試行錯誤しながら答えを導き出していくのもジギングの醍醐味だ。
まずは当たりジグだった「シックスライド」から「サーディンウェバー130g」にチェンジ。漂わせるように誘い、魚の反応をうかがう。さらに、その後はタックルごと切り替えた。
ロッドはオシアジガー インフィニティ モーティブ S610の1パワーに、リールをオシアコンクエストCT 300HG。ラインはPE1.2号、リーダーはマスターフロロ6号。ジグはペブルスティック120gを選んだ。潮止まりという状況を踏まえ、ラインを細く、ジグを軽くして、610というロングロッドを活かし、しっかりとジグを跳ね上げつつフォールを長めに入れる戦略だ。
するとこの作戦が見事ハマりヒット。上がってきたのは可愛いサイズながらも本命のヒラメ。さすが!と言える釣果だった。さらに続けてサイズアップしたヒラメをキャッチ。読みが的中し、納得の釣果を手にした。

タックルチェンジがハマり、潮止まりの中でヒラメをヒットさせた。小型だったため、すぐにリリース。

続けてヒットしたヒラメは、今回の久ノ浜、前日の相馬沖釣行を含めて最大サイズ。目標の80cmオーバーではないが、嬉しい1枚。
フォールでスライドしすぎないジグが高実績

フォールでの横への飛びが少ないシックスライドでホウボウを連発。
潮が動かない状況では、なかなか連続ヒットにつながらない。そこで山本さんは再びジグを交換。まず選んだのはシックスライド140g・Sブルピン。このチェンジが功を奏し、ホウボウを連発。さらにカサゴも追加した。この結果から「フォールで大きくスライドしないジグが有効」と判断。続いてセレクトしたのは、よりスライド幅を抑えたシックスサイド150gだ。
「シックスサイドはネチネチ探る釣りに非常に向いたジグです。サクラマスはもちろん、ヒラメにもいい。さらに根魚、タチウオ、アマダイ、マダイにも活躍します。幅広く使える万能ジグですね」
そう解説していた矢先、沖メバルがヒット。そして船長からは「最後の流し」のアナウンス。山本さんは「最後にヒラメが来ないかな?」と期待を込めてジグを落とした。するとフォールで再びアタリ。上がってきたのは尺オーバーの良型メバル。ジグセレクトの読みが当たり、根魚の反応が増え始めたタイミングでの終了は名残惜しかったが、それも釣行の一興。納得の締めくくりとなった。

プロトジグのシックスライド、シックスサイドがヒラメに非常に効果的なことが今回の釣行で分かったが、状況はいつも同じではない。やはりいろいろなジグを持ち込み、その日、その時のベストを探すことが必要だ。
水温低下が苦戦の原因。それでも楽しい海域
この日の久ノ浜沖では、朝の下げ潮はまずまず良かったものの、潮止まり後の上げ潮になると魚の活性は下がってしまった。帰港時、船長に水温の状況を聞くと、例年なら20度ほどあるはずが、数日前の台風の影響で14度まで低下。少し前にやっと18度まで回復したと教えてくれた。
船長は水温が比較的安定している場所を探してくれたが、魚は水温変化に敏感。人間にとってはわずか4度の低下だが、魚にとっては大きな変化となる。魚の行動に大きく影響するだろう。さらに上げ潮では、沖の冷たい水が浅場のボトム付近まで入り、ヒラメの活性を下げてしまった可能性もある。それでも、数は多くないながらも、船中ではヒラメをはじめ、マダイ、ブリ、各種根魚など多彩な釣果が見られ、乗船者を楽しませた。
山本さんも振り返る。
「今回はヒラメをメインターゲットとしながらも、多彩な魚種が楽しめるこの海域の魅力を感じることができました。ベストなタイミングではなかったようですが、それでも他のエリアに比べてヒラメの数が多い印象でした。海の状況が整えば、さらに素晴らしい釣果が期待できるでしょう。本来、ジグでヒラメを狙うのは簡単ではありませんが、このエリアではヒラメジギングを存分に味わえます。根魚も豊富で、とても良いフィールドですね。ぜひまた挑戦したいと思います」

福島沖の豊かさを知り、この海が気に入ったという山本さん。またタイミングをみて挑戦するようだ。
関連記事
RELATED COLUMN